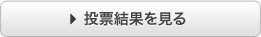ブログネタ:仕事か恋愛、どっちか一方が一生うまくいくとしたらどっち?
参加中
ブログネタ:仕事か恋愛、どっちか一方が一生うまくいくとしたらどっち?
参加中私は恋愛! 派!
本文はここから
というのが隠しテーマとおぼしきコミックを読んだので。

「x細胞は深く息をする」というタイトルのこのマンガ、かなり分厚いのですが内容がなかなか興味深くおもしろかったので一気に読んでしまいました。
*画像はクリックすると大きくなります。

この「人間もプラスチックも同じ物でできているんだよ」という言葉は、人体やプラスチックの構成要素を原子レベルで考えれば使われている元素は共通していて、元々地球上に存在したものばかりだという意味です(元素には人工的に合成されたものもあるので)。
この言葉によって導き出されたのが、自発的に収縮と弛緩を繰り返す補助人工心臓が生命のない物質から人の手によって作り出される事が可能であるという設定でした。

こう書くと、まるで題材がヒトが「非・生命」から「生命」を生み出すことについての諸々についてであるかのように思われそうですが、実は全然違っていてこの高分子ゲル(プラスチックみたいなもの)で作られた人工補助心臓って小道具にしかすぎないんですね。
これは「試験管の中で生命を生み出す」的な、例えば「鋼の錬金術師」で描かれているような、「生命はどこから来るのか」という問題を徹底的に追求する作品ではないのです。
というのも、ここで生み出されたものはあくまでも「補助」であり、心臓の弱った人に取り付けて心筋の動きを助ける役目しか担っていないからです。自発的に収縮と弛緩を繰り返すその高分子ゲルを生命と呼ぶか、或いは装置と呼ぶか、意見が分かれるところでしょう。ここでの命題はむしろ「何をもって生命と認定するか」なのでしょうね。
しかし実際の所、その命題もこの作品のテーマではありません。
高分子による人工臓器が一般的になれば、臓器移植は必要なくなるという点は何度も繰り返して語られますが、でもそれすらどこか上すべり。
というのも、この人工補助心臓を作りあげた主人公がその技術で助けたかったのはたった一人しかいなかったから。
でもその初恋の彼女は、実は15年も前に世を去っているのですよ。
だから彼が念願の人工臓器を作り出しても、ただ空しいだけだったりするのですね。
仕事しては他の追随を許さない程の成功を収めても、愛する人がこの世にいなければ何の喜びもない。恋愛が上手くいかなければ、仕事が一生上手くいったところで人生を楽しむことはできないんだと、この作品は語っているようでした。
ところがそれで「恋愛こそ人生」とうたいあげているのかというと、全然そうじゃない。
この作品には実は主人公にあたる青年は二人いるのだけど、それは要するに一人の人間を「知と情」の二つに分けたもの。「知」の方は雛形を「光と影」というか「知と情」というか、とにかく二つの側面に分けたもの。「知」は無生物=高分子ゲル(プラスチックにあたる)から、「情」はES細胞(人間にあたる)から新しく心臓を作りだそうと、どちらも孤軍奮闘しているわけです。かつて恋した一人の少女のため、彼女をしのび面影に報いるために、寝食を忘れ全てを犠牲にして開発に勤しんでいる――そんな事をしても彼女が戻ってくるわけでもないのに。
それはもはや「恋愛」というより「執着」です。
彼らが作ろうとしている人工心臓も、本当に装着させたいと思っているのはたった一人、今は亡き彼女だけなんですよね。救えなかった彼女の命の代わりに、できるだけ多くの他の命を救おうとは、彼らはあまり思ってない。
そのため「人工心臓」という、人間全ての延命を可能にするような夢のアイテムを作品に出しておきながら、その効果というか恩恵を作品は全然被っていないのですよ。これ、非常に勿体ないと思いました。
結局のところ、医療を題材にし臓器移植や人工臓器の問題をとり扱い、終末期医療や脳死判定にまで踏み込んでおきながら、この作品で描かれているのは愛する人を不治の病で失った人達の苦悩と悲嘆ばかりなのですよ。
それをここまで描けるということは、恐らく原作者の身の回りにそういう人がいたのでしょう。
そしてその時原作者が達した結論が、物語の中盤で読者にむかって投げつけるような形で出てきます。
「愛しい人の死は……」
「自分の死よりも……
でも…」
ここで何かを言ったか言葉を飲み込んだかしたらしいのですが、その一番大切な部分は誰の耳にも届かなかったという表現がなされています。
そして2コマはさんで時間の経過をあらわしてから(その間に話者は気を取り直しているわけですね)
「……人はいつか死ぬ」
呆然とその言葉を聞く人の顔が1コマあって、次ページにうつります。
「早いか遅いかは運命ですよ
それを覚悟し受け入れて生きない限り……」
「苦しみは続きますよ」
これを発言した方の主人公は当然のように世間からごうごうの非難を浴びて社会的に抹殺されます。物語が始まって3分の1ぐらいのところで主人公の一人が一旦表舞台から姿を消してしまうわけです。
それはいわば儀式としての「死」ですね。タブーに触れてしまった主人公はここで一旦形式として「死」をむかえることでいわば禊ぎを果たし、次に「復活」を果たすことができます。作品の中でそれまで死んだも同然だった彼は、これで新たな「生」を得て蘇るチャンスができたわけです。だから彼の本当の活躍というのは実はここから始まるんです。
ところがそこまでしても彼はまだ吹っ切れていず、執着はそのまま。
主人公自身が口にしたはずの
「愛しい人の死は……」
「……人はいつか死ぬ」
「早いか遅いかは運命ですよ
それを覚悟し受け入れて生き」
るのは、口で言う程たやすくはないということです。
それがこの作品の根底にずっとあるテーマというか、基本的な感情の流れなんですね。
どうすればいいのかはわかっているけれど、今はそれをしたくない。
その結果、亡き人の面影をひきずって15年。
愛した人を死によって奪われた苦しみは簡単にふっきれるものではないけれど、しかし悩んでる間にも時間はすぎるし、すぎた時間は戻りません。そしてその悩みはいずれ自分の人生を損ないます。
それでもいい、と思うほどの強い愛が実はこの作品の一番下には流れているのです。
サンクチュアリ出版 友友会ファンサイト応援中
というのが隠しテーマとおぼしきコミックを読んだので。

「x細胞は深く息をする」というタイトルのこのマンガ、かなり分厚いのですが内容がなかなか興味深くおもしろかったので一気に読んでしまいました。
*画像はクリックすると大きくなります。

この「人間もプラスチックも同じ物でできているんだよ」という言葉は、人体やプラスチックの構成要素を原子レベルで考えれば使われている元素は共通していて、元々地球上に存在したものばかりだという意味です(元素には人工的に合成されたものもあるので)。
この言葉によって導き出されたのが、自発的に収縮と弛緩を繰り返す補助人工心臓が生命のない物質から人の手によって作り出される事が可能であるという設定でした。

こう書くと、まるで題材がヒトが「非・生命」から「生命」を生み出すことについての諸々についてであるかのように思われそうですが、実は全然違っていてこの高分子ゲル(プラスチックみたいなもの)で作られた人工補助心臓って小道具にしかすぎないんですね。
これは「試験管の中で生命を生み出す」的な、例えば「鋼の錬金術師」で描かれているような、「生命はどこから来るのか」という問題を徹底的に追求する作品ではないのです。
というのも、ここで生み出されたものはあくまでも「補助」であり、心臓の弱った人に取り付けて心筋の動きを助ける役目しか担っていないからです。自発的に収縮と弛緩を繰り返すその高分子ゲルを生命と呼ぶか、或いは装置と呼ぶか、意見が分かれるところでしょう。ここでの命題はむしろ「何をもって生命と認定するか」なのでしょうね。
しかし実際の所、その命題もこの作品のテーマではありません。
高分子による人工臓器が一般的になれば、臓器移植は必要なくなるという点は何度も繰り返して語られますが、でもそれすらどこか上すべり。
というのも、この人工補助心臓を作りあげた主人公がその技術で助けたかったのはたった一人しかいなかったから。
でもその初恋の彼女は、実は15年も前に世を去っているのですよ。
だから彼が念願の人工臓器を作り出しても、ただ空しいだけだったりするのですね。
仕事しては他の追随を許さない程の成功を収めても、愛する人がこの世にいなければ何の喜びもない。恋愛が上手くいかなければ、仕事が一生上手くいったところで人生を楽しむことはできないんだと、この作品は語っているようでした。
ところがそれで「恋愛こそ人生」とうたいあげているのかというと、全然そうじゃない。
この作品には実は主人公にあたる青年は二人いるのだけど、それは要するに一人の人間を「知と情」の二つに分けたもの。「知」の方は雛形を「光と影」というか「知と情」というか、とにかく二つの側面に分けたもの。「知」は無生物=高分子ゲル(プラスチックにあたる)から、「情」はES細胞(人間にあたる)から新しく心臓を作りだそうと、どちらも孤軍奮闘しているわけです。かつて恋した一人の少女のため、彼女をしのび面影に報いるために、寝食を忘れ全てを犠牲にして開発に勤しんでいる――そんな事をしても彼女が戻ってくるわけでもないのに。
それはもはや「恋愛」というより「執着」です。
彼らが作ろうとしている人工心臓も、本当に装着させたいと思っているのはたった一人、今は亡き彼女だけなんですよね。救えなかった彼女の命の代わりに、できるだけ多くの他の命を救おうとは、彼らはあまり思ってない。
そのため「人工心臓」という、人間全ての延命を可能にするような夢のアイテムを作品に出しておきながら、その効果というか恩恵を作品は全然被っていないのですよ。これ、非常に勿体ないと思いました。
結局のところ、医療を題材にし臓器移植や人工臓器の問題をとり扱い、終末期医療や脳死判定にまで踏み込んでおきながら、この作品で描かれているのは愛する人を不治の病で失った人達の苦悩と悲嘆ばかりなのですよ。
それをここまで描けるということは、恐らく原作者の身の回りにそういう人がいたのでしょう。
そしてその時原作者が達した結論が、物語の中盤で読者にむかって投げつけるような形で出てきます。
「愛しい人の死は……」
「自分の死よりも……
でも…」
ここで何かを言ったか言葉を飲み込んだかしたらしいのですが、その一番大切な部分は誰の耳にも届かなかったという表現がなされています。
そして2コマはさんで時間の経過をあらわしてから(その間に話者は気を取り直しているわけですね)
「……人はいつか死ぬ」
呆然とその言葉を聞く人の顔が1コマあって、次ページにうつります。
「早いか遅いかは運命ですよ
それを覚悟し受け入れて生きない限り……」
「苦しみは続きますよ」
これを発言した方の主人公は当然のように世間からごうごうの非難を浴びて社会的に抹殺されます。物語が始まって3分の1ぐらいのところで主人公の一人が一旦表舞台から姿を消してしまうわけです。
それはいわば儀式としての「死」ですね。タブーに触れてしまった主人公はここで一旦形式として「死」をむかえることでいわば禊ぎを果たし、次に「復活」を果たすことができます。作品の中でそれまで死んだも同然だった彼は、これで新たな「生」を得て蘇るチャンスができたわけです。だから彼の本当の活躍というのは実はここから始まるんです。
ところがそこまでしても彼はまだ吹っ切れていず、執着はそのまま。
主人公自身が口にしたはずの
「愛しい人の死は……」
「……人はいつか死ぬ」
「早いか遅いかは運命ですよ
それを覚悟し受け入れて生き」
るのは、口で言う程たやすくはないということです。
それがこの作品の根底にずっとあるテーマというか、基本的な感情の流れなんですね。
どうすればいいのかはわかっているけれど、今はそれをしたくない。
その結果、亡き人の面影をひきずって15年。
愛した人を死によって奪われた苦しみは簡単にふっきれるものではないけれど、しかし悩んでる間にも時間はすぎるし、すぎた時間は戻りません。そしてその悩みはいずれ自分の人生を損ないます。
それでもいい、と思うほどの強い愛が実はこの作品の一番下には流れているのです。
サンクチュアリ出版 友友会ファンサイト応援中